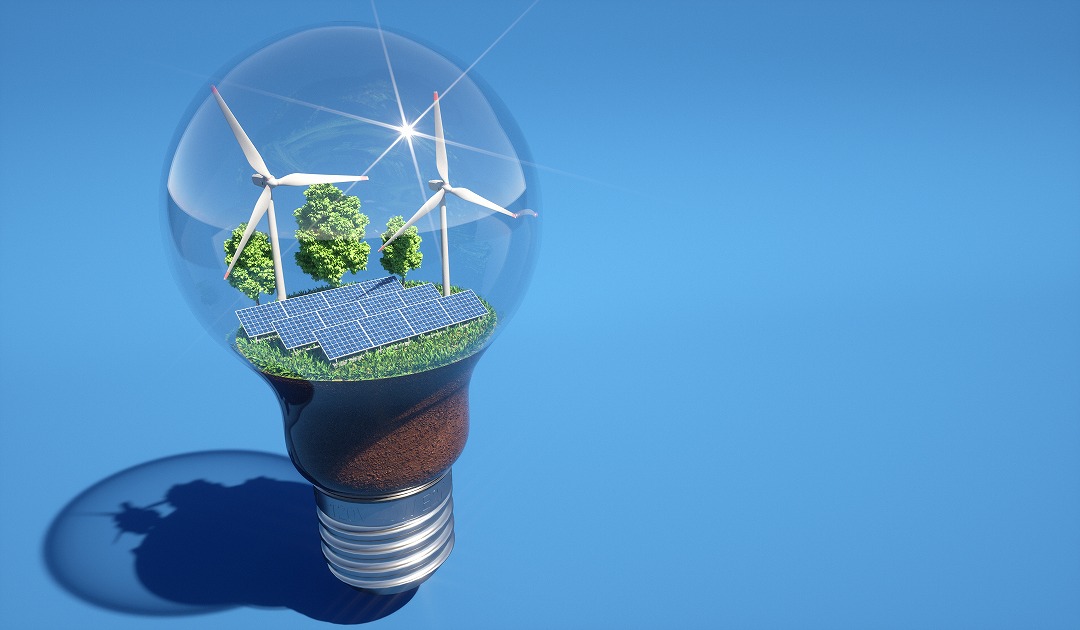- ALL
- CORPORATE
- BUSINESS
- OTHERS
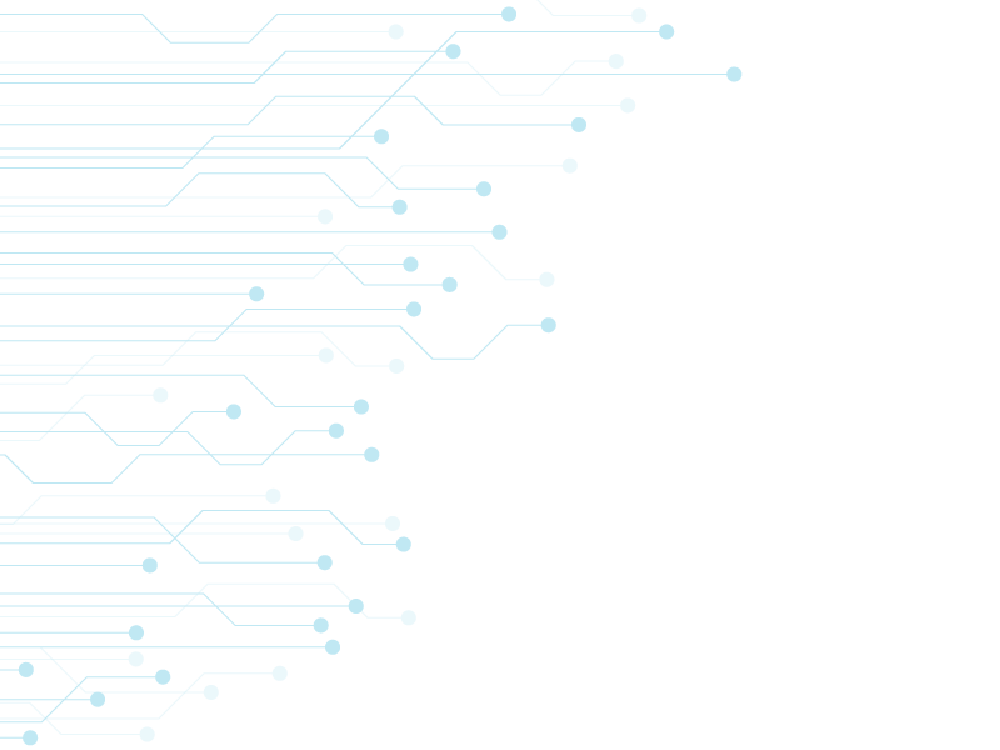
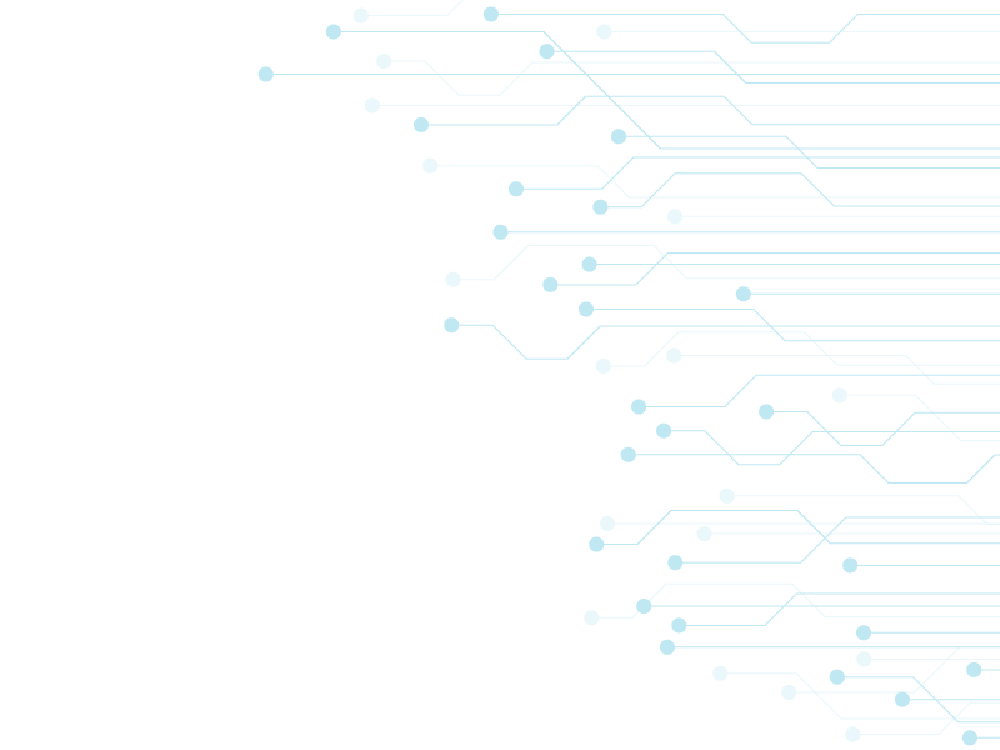
データセンター、
そしてデジタルインフラの
持続可能な未来のために
日本におけるデータセンター投資はまさに活況を呈しており、今後も需要が高まっていくと想定されます。その一方で、膨大な電力消費を伴うことに対する警鐘が鳴らされているのも事実です。 また、東京・大阪を中心とするエリアでの建設が集中する傾向にあり、日本の国策である「データセンターの国内最適配置」の実現への道のりは、厳しいと言わざるを得ません。土地保有者・データセンター事業者・デベロッパー・投資家・エネルギー事業者・データセンター設備関連事業者・政府・自治体…、ステークホルダー全員が同じ想いでデータセンターやデジタルインフラ*を整備・活用するプロジェクトを組成し、その伴走者となるべく、私たちデジタルインフラ・ラボ(DIL)は存在します。
*データセンターに限らず、eコマース物流施設、デジタル関連のLab、基地局・通信網、再生可能エネルギーの分野を対象としています。
“あるべき”デジタルインフラ投資を実現するために
- ALL
- TOPICS & NEWS
- Founder Message
- ESG + DC
2026.01.26
KDDI、大阪堺データセンターが稼働開始 〜AI需要をにらむ内資系データセンター事業の本格始動〜
通信大手のKDDIは2026年1月22日、大阪府堺市に新設した「大阪堺データセンター」の稼働を開始しました。これにより、AI処理需要の増大を背景に国内のデータセンター(DC)事業が再び動きを見せています。ここ数年目立った新設がなかったKDDIのDC事業ですが、昨今のAIインフラ需要を踏まえた戦略的な一歩と捉えられています。

大阪堺データセンター外観
シャープ堺工場跡地の再活用と短期間構築
大阪堺データセンターは、2025年4月にKDDIが取得した旧シャープ堺工場の跡地に構築されました。広大な敷地に元々備わっていた大規模な電力・冷却インフラを再利用することで、約半年という短期間での稼働開始を実現しています。従来のDC構築で必要となる長期の設備整備を大幅に圧縮できた点は、他社事業者との差別化要素として注目されます。
この施設は地上4階建て、延床面積約57,000平方メートルと大規模で、使用電力は100%再生可能エネルギー由来とする環境配慮型の設計も特徴です。電力供給と冷却は直接液体冷却(DLC)方式を取り入れ、高性能計算処理と低消費電力の両立を図っています。
AI処理インフラとしての機能強化
新データセンターには、NVIDIA製のAIサーバー「GB200 NVL72」など最新世代GPUサーバーが導入されており、AI学習や推論処理に最適化されたインフラとして位置づけられています。さらに、Googleの生成AIモデル「Gemini」のオンプレミス提供など、パートナー企業との協業を通じたサービス開発基盤としても活用される計画です。
法人企業向けにはGPUリソースの提供も行われ、多様な業界でのAI社会実装を支える役割が期待されています。特に製薬や製造などデータ量が巨大になりやすい分野では、高度な計算基盤のニーズが強まっており、KDDIはこの流れを捉えた形です。
30年以上の知見の集積と国内DC事業の潮流
KDDIはTelehouse渋谷データセンターで培った水冷技術やDC構築のノウハウを活用し、大阪堺データセンターの設計・運用に生かしています。これにより、高い稼働率や安定性を保ちながらも、新技術対応への柔軟性を確保しています。
国内ではソフトバンクも旧工場跡地を活用した大型DCプロジェクトを進めており、内資系事業者による大型インフラ投資の動きが活発化していることが読み取れます。AI処理需要の高まりを背景に、データセンター事業は従来の通信インフラの枠を超え、産業全般のデジタル基盤としての重要性を増しているといえるでしょう。
2026.01.19
グッドマンが日本で加速するデータセンター展開
物流ファンドのグッドマンは、これまで物流施設を中心に日本各地で事業展開を進めてきましたが、近年はデータセンター(DC)事業への進出を着実に進めています。特に千葉・茨城・神奈川圏を中心に、先進的なデジタルインフラの整備が進展しており、日本国内のデータセンター事業に新たな潮流を生み出しています。
印西におけるSTT GDCとの協業
千葉県印西市は、東京都心からのアクセスが良い立地と安定した電力供給などを背景に、データセンター集積地として知られています。こうした環境を活かし、シンガポール発のデータセンター事業者であるSTテレメディア・グローバル・データセンターズ(STT GDC)が、グッドマンの開発する施設内でデータセンターを展開しています。
2025年には日本国内初となる「STT Tokyo 1」が稼働し、約32MWのIT電力を提供可能な大規模DCとして運用が始まりました。将来的には同キャンパス内で2棟目となる「STT Tokyo 2」も建設され、さらなる処理能力の拡充が見込まれています。
このように、グッドマンが開発する施設をSTT GDCが活用する形で、先進的なデータセンターインフラの早期整備が進んでいます。
つくばにおける大型キャンパスの計画
一方、グッドマンは茨城県つくば市でも大規模なデータセンターキャンパスの計画を進めています。つくば市では広大な敷地を活用し、1棟目のデータセンターが2026年に完成予定です。このキャンパスでは最大1000MW級の電力供給体制を視野に入れ、段階的に複数棟のDC建設が進められる構想とされています。
つくばは先端研究機関が集積する科学都市としての特性を持ち、AIやクラウド関連の需要増加とも相まって、データセンター立地としての優位性が高まっています。
相模原での展望と地域期待
神奈川県相模原市に関しては、現時点で公式な建設計画の発表はありませんが、地元ではグッドマンによるデータセンター進出の可能性が取り沙汰されています。相模原は東京圏へのアクセスが良好で、道路・電力インフラの整備状況からもDC立地に適した条件を備えており、今後の動向に注目が集まっています。
デジタル基盤を支える拠点戦略
グッドマンのデータセンター展開は、物流施設を中心とした従来の事業領域から、デジタルインフラの整備へと領域を広げている点が特徴です。印西でのSTT GDCとの協業、つくばでの大規模キャンパス整備、そして相模原での期待感と、複数地域での動きが連動しながら、日本のデータセンター基盤の充実に寄与しています。今後も各地域での展開が進むことで、国内のデジタル基盤はさらに強化されていくと見込まれます。
海外プレイヤー参入の可能性と市場環境の変化
今後の日本市場では、国内デベロッパー主導の開発に加えて、海外の通信・データセンター系プレイヤーとファンドが連携して参入してくる動きが更に活発化してくると考えられます。たとえば、不動産ファンドのSC Capital Partners と海外でデータセンター開発・運用を手がけるSC Zeus Data Centersが、首都圏近郊の電力・用地条件に着目し、日本での拠点構築を積極的に展開しつつあります。AI・クラウド需要の拡大を背景に、日本のデータセンター適地は国際的にも魅力を高めています。
また、アジア太平洋地域で強いプレゼンスを持つ通信事業者である シンガポールテレコム(Singtel)についても、グローバルネットワークとデジタルインフラ投資の延長線上で、日本市場との関わりを今後深めていく可能性があると見られます。こうした海外勢の動きは、国内データセンター市場の競争環境や開発スピードに影響を与える要因のひとつになっていくでしょう。
こうした中で、日本でのデータセンター開発を検討する事業者にとっては、用地条件や電力インフラ、行政対応など、日本特有の環境を踏まえた検討がより重要になります。
2025.12.23
2025年のデータセンター市場を振り返る―多様なプレイヤーが動いた一年
2025年のデータセンター市場は、結果としてこれまで以上に多様なプレイヤーが参入し、プロジェクトの大規模化が一段と進んだ一年となりました。生成AIの急速な普及やクラウド利用の拡大を背景に、日本市場は国内外の事業者から中長期的な成長が見込まれる市場として改めて注目を集めました。
この年を通じて特徴的だったのは、参入主体の広がりです。従来は国内大手事業者や一部の外資系企業が中心でしたが、2025年は不動産デベロッパー、インフラ投資ファンド、通信関連企業、さらには海外で豊富な運営実績を持つデータセンター専業事業者など、背景の異なるプレイヤーが同時に存在感を高めました。
また、施設の在り方も変化しました。単なるコロケーション提供にとどまらず、AIワークロードを前提とした高電力・高密度設計や、ハイパースケーラー対応を見据えた大規模キャンパス型開発が進み、市場全体として「多様化」と「大規模化」が並行して進んだ一年だったと言えるでしょう。
立地面でも動きがありました。首都圏や関西圏の既存エリアに加え、新たな地域や準主要都市への進出が相次ぎ、日本国内のデータセンター立地はより広域的な広がりを見せました。
2025年を象徴するデータセンター各社の動き
2025年の市場動向を象徴する事例として、ESRの動きが挙げられます。ESRはStack InfrastructureやColt DCSとの連携を通じて、大阪・南港という新たなエリアへ進出しました。これは、関西圏におけるデータセンター立地の選択肢が広がったことを示す象徴的な動きでした。
Gaw CapitalとDayOneの連携も、2025年を特徴付ける動きの一つです。シンガポール系資本を背景に持ちながら、本社は中国に置くデータセンター事業者であり、日本市場にはこの年が実質的な初進出となりました。GDSを含め、中華系データセンター事業者の存在感が日本でも可視化された一年だったと言えます。
さらに、FLOW Digital InfrastructureやEdgeConneXといったグローバルなデータセンター専業事業者も、2025年に日本市場へ初めて参入しました。海外市場での運営ノウハウを持つ事業者が相次いで日本に拠点を構えた点は、市場の成熟度が一段階進んだことを示しています。
Global Compute Infrastructure(GCI)は北九州への進出を通じて日本市場に参入し、地方都市におけるデータセンター開発の可能性を具体的に示しました。また、Princeton Digital Group(PDG)は、さいたま市において初の大型データセンター開発を進め、首都圏近郊における大規模案件として存在感を高めました。
2025年は、多様なプレイヤーがそれぞれの強みを持ち込み、日本のデータセンター市場に新たな選択肢と広がりをもたらした一年でした。こうした動きは、今後のデータセンターの在り方や立地戦略、事業モデルを考える上で、重要な示唆を与えるものとなっています。
2025.12.21
生成AI時代、データセンター建設費という新たな注目ポイント
生成AIの普及を背景に、データセンターを取り巻く環境は大きく変化しています。これまでデータセンターの課題としては、電力需要の増大や電力インフラの確保が注目されることが多くありましたが、近年ではそれに加えて「建設費」の動向にも関心が集まりつつあります。
こうした中、ターナー&タウンゼントが発表した最新の調査では、世界各都市におけるデータセンター建設コストが比較され、日本の都市が非常に高い水準にあることが示されました。特に東京は、1ワットあたりの建設費が世界でもトップクラスとされており、日本市場の特徴を改めて浮き彫りにする結果となっています。
生成AI向けのインフラ需要が拡大する中で、データセンターの建設費は、今後の投資判断を考える上で無視できない要素となりつつあるようです。
建設費が高水準となる背景
今回の調査では、日本のデータセンター建設費が高水準となっている背景として、いくつかの要因が挙げられています。その一つが、生成AI対応に伴う設備要件の高度化です。高密度なサーバー配置に対応するため、電力供給設備や冷却設備の仕様が引き上げられ、結果として建設費全体が押し上げられています。
また、電力・空調・IT設備といった専門分野に対応できる人材の確保が難しくなっている点も、コスト上昇の一因とされています。加えて、海外からの資材調達や為替の影響を受けやすい構造もあり、こうした複合的な要素が日本の建設費水準に反映されていると考えられます。
今後の動向として注目されるポイント
生成AI市場の成長が続く中で、データセンター需要は今後も堅調に推移すると見込まれています。それに伴い、建設費についても短期的に大きく下がるというよりは、高水準で推移する可能性があるとみられています。
一方で、こうした状況を受けて、建設手法やプロジェクト管理の工夫によってコストの最適化を図ろうとする動きも出てきています。建設費の動向は、電力や立地と並ぶ重要な検討項目として、今後さらに注目されていくことになりそうです。
生成AIの時代において、データセンターを支えるインフラの在り方は引き続き変化していきます。その中で、建設費という視点から市場動向を捉えることは、今後のデータセンターを取り巻く動きを理解する上での一つの参考材料になるといえるでしょう。
2024.08.23
政府は、産業集積や補助金支給によって国内データセンターの脱酸素化に期待
人工知能(AI)の急速な普及に伴い、データセンターの重要性が増しています。現状では生成AIや数年後のAIを支えるデータセンターが不足する可能性があり、データセンターで消費する大量の電力をどう確保するかなどの課題を抱えています。各社は再生可能エネルギーを利用し、二酸化炭素(CO2)の排出量を抑えながら、需要に対応できるよう工夫を凝らしている状況もありますが、国内の企業はまだそこまで意識は高くない傾向にあります。
GAFAMは自社で再生可能エネルギー発電所を建設
アマゾンなどGAFAMはすでに、発電事業者と長期契約を結んで再エネを直接調達しています。データセンターなど電力を消費する施設の近くにある再エネ発電設備を確保して、「地産地消」のかたちで再エネを使用しています。
米Google(グーグル)は、再エネ電源を50カ所以上、合計容量は5.5GWを調達していることを明らかにしています。米Microsoft(マイクロソフト)は世界10カ国で5.8GWの再エネ電源の調達契約を発表しています。
政府、補助金支給の仕組みを検討
そんな中、政府は再エネや原子力といった脱炭素電力が豊富な地域への産業集積を進めることを発表しました。工場やデータセンターなどを建設する際、企業と地方自治体による投資計画を審査し、脱炭素の度合いが高い案件を法人税優遇や補助金支給の対象とする仕組みを検討。
政府の脱炭素戦略を定めたグリーントランスフォーメーション(GX)推進法を改正。企業の拠点整備に関して、脱炭素電力の使用割合などを明記した計画を策定してもらう予定です。
域内で使う電力の一定程度以上を脱炭素型でまかなう自治体との申請を条件とすることで、環境負荷低減を軸とした企業立地政策への転換を狙います。
認定を経て、企業は法人税の軽減や設備投資への補助金支給といった措置を受けられます。
脱炭素化に向けて、企業の意識の変容に期待
国内で脱炭素電力を供給できる地域には偏りがあります。太陽光や風力と言った再エネや原子力による発電施設が多く立地し、脱炭素の電源比率が4割を超える地域は国内で北海道と関西、九州だけとなっています。風向きに左右される洋上風力の適地は北海道や青森県、秋田県、長崎県などの沖合に限られます。
発電所から遠くに電力を運べば、送電ロスが発生します。送電網設備にもコストがかかり、遠隔地からの電力の使用は割高となります。産業集積によって電力の地産地消を促し、エネルギーの効率的な利用につなげます。
国内では近年、半導体関連の工場建設に加え、データセンターの新設が活発になっています。電力消費の増加が見込まれる一方、政府は50年までにCO2など温暖化ガスの実質排出ゼロを目指しています。
補助金支給によって企業の意識が脱炭素化に向かっていくことが期待されますが、実際はどうなるのか。今後の状況も紹介していきたいと思います。
2023.07.05
アイルランド政府のデータセンター開発モラトリアムに、Googleが反発
アイルランド政府、データセンター開発に制限
アイルランドの公益事業規制委員会(CRU)が、ダブリン大都市圏での新しいデータセンター開発に事実上のモラトリアムを課し、影響を制限する決定を下しました。
アイルランドの国営送電事業者EirGridは、それを受けて、ケースバイケースでグリッドへの接続のための新しいアプリケーションのみを検討すると述べました。伝えられるところによると、制限は2028年まで続く可能性があります。
アイルランド政府産業開発庁(IDA)のマーティン・シャナハン最高経営責任者(CEO)は最近、新しいデータセンターは「現時点では、ダブリンと東海岸で発生する可能性は低い」と述べています。
Googleはこのようなアイルランドの規制当局に対し、同国のデータセンター開発にモラトリアムを強制しないよう求めています。
同社は公益事業規制委員会(CRU)への提出書類で、検索およびクラウド会社は、データセンター開発のモラトリアムは「絶対に」回避する必要があると述べました。
アイリッシュ・タイムズ紙が情報公開請求により最初に報じたところによると、Googleはこのような禁止措置はアイルランドのデジタル経済としての野心について「誤ったシグナル」を送ることになり、同国のインフラへのさらなる投資を「不可能」にすると付け加えています。
提出書類の中でGoogle は、アイルランドのネットワークに既存の電力容量がある場所についてより透明性を求めるとともに、データセンターの電力使用量の伸びを予測するEirGridの予測について、より明確でオープンなものにする必要があるとしています。
高まるクラウドコンピューティングの需要、Googleの提案
2012年にアイルランドで最初のデータセンターを立ち上げた Googleは、最終的に必要とする以上の容量を予約したり、その容量に成長するのが遅すぎるデータセンター事業者に対する新しい料金体系を提案しました。
「最大予約容量に向かって需要が増加していない消費者は、毎年増加していることを実証している消費者よりも多く請求されるように、送電料金制度を設計することができる」と述べています。
EirGridと政治家は以前、データセンターの開発をアイルランド西部(ダブリンの制約のある地域から離れ、再生可能エネルギー源に近い場所)に移すことを提案しましたが、Google はこれが実現可能な解決策ではないと指摘しています。
「ダブリンでのクラウドコンピューティングの需要は高まっています。多くのクラウドサービスはユーザーの近くにあるデータセンターで提供する必要があり、ダブリンから遠く離れたデータセンターでは、顧客の必要に応じてこれらのサービスを提供することはできません。」
AWSの別の提出書類では、アイルランドは過去に供給問題に対処する機会を逸してきたと述べています。
「これまでの10年間、補強工事を行い、成長と投資に備えた送電網を整備し、より断続的な資源の統合に備えた送電網を整備する機会があった」と述べています。
社会民主党とPeople Before Profitの両党は、過去12ヶ月間、将来のデータセンタープロジェクトの全国的なモラトリアムを求めてきました。PBPの法案は、データセンター、液体天然ガスプラント、新しい化石燃料関連のインフラを絶対禁止とするものでした。
ダブリンでは先月、南ダブリン郡議会(SDCC)が新しい開発計画案の一環として、同郡での今後のデータセンター建設を阻止することを決議しています。
では、アイルランド政府のデータセンター開発モラトリアムには、どのような背景があるのでしょうか。
アイルランド政府、データセンター開発モラトリアムの背景
アイルランド政府による、排出量と再生可能エネルギーの目標の達成が背景にあります。
EirGridによると、データセンターのエネルギー使用量は、2030年までに9TWh増加すると予測されており、2030年のアイルランドの送電網の供給量の23%から31%の範囲で予測されています。これは、政府が自然エネルギーの割合を増やすことで、排出量を60〜80%削減したいと考えている時期にあたります。同時に政府は暖房や輸送を電気に移行することで脱炭素化を図りたいと考えており、送電網の需要をさらに高めています。
アイリッシュ・タイムズ紙によるとEirGrid社はさらに1.8GWのデータセンターをグリッドに接続することに合意しており、現在のピーク時の需要は約5GWで、さらに2GWのアプリケーションが準備されているとのことです。
2018年に発表された「アイルランドの企業戦略におけるデータセンターの役割に関する政府声明2018」 (Government Statement on the Role of Data Centres in Ireland’s Enterprise Strategy 2018)では、国の経済パフォーマンスにおいてデータセンターに積極的な役割を与えていましたが、今後は「セクターごとの排出量の上限や再生可能エネルギーの目標、継続的な供給の安全性に関する懸念、現在必要とされている需要の柔軟性対策との整合性を確保するため」に見直されることになりました。「また、さらなる規制の強化も検討されます」と報じられています。
功を奏するのか裏目に出るのか
世界的にも需要が高まるデータセンター開発にモラトリアムを課すアイルランド政府。Googleからの反発を受けながらもモラトリアムを継続する様子。この決断が功を奏するのか、裏目に出るのか。動向を見守っていきます。
2023.03.26
データセンターの設備点検業務ロボット2023年4月から本格展開(NTTデータ)
株式会社NTTデータは、同社が運営するデータセンター「NTT品川TWINS DATA棟(以下、品川データセンター)」において、ロボットを使った設備点検業務の遠隔化/自動化の取り組みを行い、従来人手で行われていた設備点検業務を約50%削減できることを確認したことを発表しました。
NTTデータは2023年4月以降、全国のデータセンター拠点へのロボット導入を進めます。
ロボット導入の背景
NTTデータでは、データセンターをはじめとしたビル管理業界では人手不足が深刻化しており、中でも設備管理業務は熟練者の不足が問題となっており、省人化や効率的な業務実施が求められていると説明。
設備管理業務の中では、点検業務が省人化による効果やデジタル技術活用による遠隔化/自動化の実現性が高いと考え、同社の品川データセンターにおいて、実用化に向けた検証を進めてきました。
ロボット導入の概要と変化するチェック業務
取り組みでは、あらかじめ設定した点検ルートをロボットが自動巡回し、メーターやランプ、設備外観の撮影、センサーによる臭気など環境データの取得を行うことで、人が行っていたメーター測定やランプ確認、外観異常・異臭チェックの業務を代替します。
この方法の場合、1つのカメラやセンサーで複数箇所の点検を行え、稼働中の現用設備に手を入れる必要もないため、点検対象ごとのIoTカメラ・センサーの設置やスマートメーター化といった他の方法と比較して、安価かつ簡易に遠隔化/自動化を実現できます。
今回用いたロボットは、業務DXロボットのメーカーであるugo株式会社と共同で、次世代型アバターロボット「ugo Pro」を設備点検業務用に改良したものです。
メーター値を詳細に撮影するため、標準モデルより高画質な4Kカメラを搭載するとともに、においセンサーやマイク、サーモカメラなど、点検項目に応じて複数のデバイスをugo本体に搭載し、用途を拡大できます。
PCのみで操作が可能で、走行ルートもノーコードで設定できるため、現場担当者も気軽にロボットを利用できます。自動走行と遠隔操縦を切り替えられ、自動で点検業務を行うだけでなく、遠隔からの作業支援など複数の用途で利用も可能です。
これらの特徴により、さまざまな点検項目に対応できるだけでなく、遠隔からの作業支援や工事の立ち合いなど用途を拡大することも可能です。
ロボットやセンサーを使って点検業務を遠隔化/自動化することで、業務時間が削減できるだけでなく、人の感覚に頼っていた異常判断のしきい値を数値化し、熟練者に頼らない異常発見を実現できます。
また、作業支援や工事の立ち合いなども含め、現地でしかできなかった業務を遠隔で実施可能にすることで、柔軟な働き方に対応し、新たな担い手の確保等の効果が期待できます。
今後について
NTTデータでは今後、メーター読み取りシステムや異常検知AIとの連携を進めることで、現在担当者による実施が必要となる記録・報告作業まで自動化範囲を拡大し、点検業務にかかる時間を最大80%削減することを目指しています。
また、ロボットやセンサーで取得したデータを活用した高度な異常検知や設備の予知保全といった、設備管理業務の高度化にも取り組んでいくとのことです。
2023年4月から、全国15のデータセンターを対象として、取り組みを順次展開していく予定。
さらに、これらにより得られた知見をもとに、2023年度中に設備点検業務の遠隔化/自動化サービスとして商用提供することを目指します。
商用提供にあたっては、ugoがNTTデータとの共同検証で得られた知見を生かして開発した新型ロボット「ugo mini」を活用した設備管理業務の遠隔化/自動化ソリューションの開発を行い、導入のコンサルティングからシステム構築・運用までワンストップで、顧客の課題解決をサポートしていきます。
深刻化する人手不足の解消に向けて、データセンターの設備点検業務ロボットの本格展開の日が待たれます。
2023.03.11
北海道石狩市で計画する「ゼロエミッション・データセンター」の着工を発表(KCCS)
京セラコミュニケーションシステム株式会社(以下、KCCS)は24日、北海道石狩市で計画する「ゼロエミッション・データセンター」について、2022年12月にデータセンター建設に着工し、2024年秋に開業を予定すると発表しました。
KCCSでは2019年に、北海道石狩市において、再生可能エネルギー100%で運営するゼロエミッション・データセンターの計画を発表。
その後、当初予定していたベースロード電源の計画変更により、電源構成およびデータセンター設計を見直していましたが、今回、建設着手と開業予定を発表しました。
建設するデータセンターは、北海道石狩市の石狩湾新港地域に位置し、敷地面積は約1万5000㎡、延床面積は約5300㎡(開設時)、ラック数は400ラック規模(開設時)。
2050年カーボンニュートラル実現に向けて
国内では2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)の達成に向けた再エネの地産地消や、政府が推進する「デジタル田園都市国家構想」におけるデータセンターの地方分散が重要なテーマとなっており、非化石証書等の環境価値の購入により環境負荷をプラスマイナスゼロにする「実質再エネ」の導入が進んでいます。
そのために、再エネ導入量のさらなる拡大に向けて、「再エネの直接利用」の拡大も必要とされます。
しかし、データセンター等の大規模な需要施設においては安定した再エネ電力と経済性の確保が課題となっており、「再エネの直接利用」の実現は容易ではありません。
石狩市は、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、環境省の公募事業「脱炭素先行地域(第1回)」に選定されています。
また、ゼロ・カーボンに向けた施策「再エネの地産地活・脱炭素で地域をリデザイン」を策定し、石狩湾新港地域にデータセンター群および周辺施設へ再エネを供給することで、脱炭素型の産業集積を目指しています。
ゼロエミッション・データセンターでは、地域の豊富な再エネ電源を活用するとともに、KCCSの所有の太陽光発電所をデータセンターの近隣に新設し、それらの再エネ電源を直接利用することになります。
また、複数の再エネを「信頼性」「環境性」「経済性」を同時に確保しながらデータセンターを運営するために、蓄電池とAI技術を活用した電力需給制御の仕組みを独自に構築します。
KCCSでは、石狩市における「再生可能エネルギー100%で運営するデータセンター事業」を通じて、再エネの地産地消の可能性を実証するとともに、国内でのデータ分散保管や、データセンター技術者・エネルギー関連技術者などの雇用創出による地域活性化への貢献を目指すとしています。
2050年カーボンニュートラル実現に向けて「ゼロエミッション・データセンター」の開業に、期待が高まっています。
2022.09.05
その4:最終回 – データセンター(DC)とカーボンニュートラル
DCの最適配置に向けて地方分散とカーボンニュートラルへ向けて成功するキーワード
地球温暖化や異常気象、CO2対策、SDGs及びESG投資のキーワードは、企業レベルにとどまらず、今や国民一人一人にも浸透し意識レベルが向上しています。
ちょっと視点を変えますが、今日までのコロナ禍において、世界では外出禁止令等法規制という強い措置をもってコロナ対策をしていましたが、日本では法による罰則がなくても殆どの事業者及び個人は、国が指導する3蜜対策、リモートワーク、営業自主規制、マスク着用等々を成功させています。日本人の国民性が自己の権利・主張のみならず、周囲への配慮、気遣いができる義務を重んじる国民性であることが、改めてコロナを通じて再認識したのではないでしょうか。
DCの最適配置における地方分散の実現も、我が国の国民性を活用して成功するキーワードがあるような気がします。
その3で説明した通り、国内のDC利用者が都市部に集中するのであれば、DC利用者に対し、地方の一定の基準を満たした新たなDCを活用することを国が指導し、一定の恩恵を与えることで、DCの最適配置に向けての課題は解消できるのではないかと考えています。
では、地方の一定の基準を満たした新たなDCとはどのようなものにすればよいでしょうか。
DCの開発先例からみてみると、株式会社データドックは新潟県長岡市に今まで類を見ないハイスペックの寒冷地型DCを建設しました。JDCC:ティア4のみならず、PUE値:1.19、床荷重:3.0t/㎡、雪氷冷熱設備の装備、産学連携による余剰エネルギーを活用した植物工場の誘致、その他の耐災害性等々、環境にやさしく、DC利用者が安全・安心してサーバーを設置することが可能なDCとなっています。これらの性能を各方面から評価を受けた結果、世界でトップクラスのサーバーベンダーであるNVIDIAが独自の高い基準による自社のサーバーを設置するために推薦する「NVIDIA DGX-Ready Data Center」として、アジアの7社の1つに認定すると共に、国内においてDCでは初めてとなるJクレジットの認証を受けました。
地方の一定の基準を満たした新たなDCとは、上記を参考として国が一定基準を設けてクリアしたDCのみに与える(仮)認証エコDCとして地方誘致促進を図り、一定規模のサーバーを保有する企業(主に大企業や中堅企業)に対して(仮)認証エコDCにサーバーを置くことを指導する仕組みです。指導に従った企業には、一定の税制措置の優遇や、認証マークの企業広告の活用を可能にして、企業側のESGへの取組みPRに最大限活用してもらいます。加えて、クラウド事業などを展開する企業にとっては、中小企業や個人のエッジコンピューターを利用している相手方に対して、(仮)認証エコDCにサーバーを設置していることをPRして、エッジの利用者のクラウド利用促進を図り、エッジの利用者も間接的にCO2削減に貢献していることを認識させる仕組みです。
その3でDC利用者の都市部での利用が心理的要因であるならば、上記の方法は功を奏することに違いなく、発展形として(仮)認証エコDC周辺にICT系企業の地方誘致促進につながり、地方創生の一助にもなるのではないかと考えています。
(仮)認証エコDCの認定基準ですが、DCがカーボンニュートラルへとより近づくために、認証基準のハードルはより高く、可能な限りPUE値を低く且つ再生可能エネルギーを最大限活用したDCであるべきと考えています。
最後になりますが、このブログが国または地方公共団体のデジタルインフラ関連のご担当者の目に留まり、日本のデジタルインフラの発展の一助となるような、有益な展開になることを切に願っております。
(文責:小杉 雅芳)
以上
2022.09.05
その3:データセンター(DC)とカーボンニュートラル
DCの最適配置に向けての地方分散と現状の矛盾について
国内のDCの立地を見ると、約8割が関東及び関西に集中してるのが現状です。これは大規模地震等の災害に対して脆弱な立地であり、BCP(Business continuity plan:事業継続計画)の観点から大きな問題となっています。また、これらDCの約40%以上が竣工後20年以上を経過していると共に低電力DC(2kVA/ラック以下)の割合が約60%以上を占めている状況で、加速度的に進むAIや深層学習需要等に対応するDCの提供が難しくなっています。加えて、我が国のデジタル化は欧米諸国やアジア圏諸国と比べ遅れを取っており(世界デジタル競争力ランキング2020で27位)、残念ながらデジタル後進国と言わざるを得ない状況です。
現岸田政権においては、2021年12月の所信表明演説で「成長と分配の好循環を実する「新しい資本主義」をコロナ禍に伴う危機後の目標に位置づけ、成長戦略の柱として①イノベーション②デジタル③気候変動④経済安全保障の4分野を掲げ、デジタル分野では日本を周回する海底ケーブル「デジタル田園都市スーパーハイウェイ」、大規模データセンターや光ファイバー、高速通信規格「5G」と組み合わせて高速大容量インフラの全国での整備を実現する」ことを約束しました。その結果を受けて、DCの最適配置に向けて地方分散の提案が徐々に取り纏まりつつある状況で、現在では多数の地方公共団体も名乗りを上げている状況となっています。
それでは、国が推し進めるDCの最適配置(地方分散)が順調にいけばよいのですが、はたしてどうでしょうか。
今、私たちが肌で感じていることは、新たにDC事業を企てているDC事業者等は、東京であれば東京23区内又は大手町から30〜50㎞圏内のDC用地を、大阪であれば大阪市内(内陸側)又は堂島から30〜50㎞圏内(且つ北摂及び京阪奈エリア)のDC用地を血眼になって探しています。東京23区内や大阪市内においては、都市型DCの建設を目論み、その30〜50㎞圏内には、ハイパースケールDCの建設を目論んでいます。つまり現状においては、我が国が進めるDCの最適配置と矛盾した状況が現場レベルでは進んでいるのが現状です。実は簡単なことで、DC事業者はサーバールームをDC利用者(サーバー設置を希望する企業等)に場所を提供して収益を上げる構造で成り立っていますが、DC利用者自体の需要が上記のエリアを希望していることが大きな要因となっています。当社の経営陣も地方でDC事業をしていた際、DC利用者の呼び込みに大変苦労していたようです。DC利用料金を都市部より安価に設定して営業攻勢をかけても、DC利用者から聞こえてくる声は「大手町、堂島のIXに近い方がレイテンシーの観点から安心」、「有事の際、事務所から1時間以内で駆け付けられる場所が理想的」、「BCPの観点からは地方分散をするべきであるが、大規模な天災直後は、社内経営陣も含め重要性は認知するものの、時の経過と共にトーンダウンしてしまう」等々、心理的要因が大きな影響を与えています。レイテンシーの観点で言えば、海外にサーバーを置くわけではなく、国内の強力な通信網と繋がったDCであれば、時間のずれはごく僅かです。事務所から1時間圏内も、複数の地方DCにバックアップ対策を講じていれば、概ね解消できる議論であり、かつ、各DCにおいても、各利用者の要請に応じてサーバーのマネージドサービスを提供しているのが一般的です。
このような状況下、DCの最適配置に向けて地方に積極的にDCを誘致しても、DC事業者が積極的に手を挙げて、DC事業を展開していくにはハードルが高く、如何にしてDC利用者に地方進出に目を向けさせるかが課題となります。
(その4:最終回)ではDCの最適配置に向けて地方分散とカーボンニュートラルへ向けて成功するキーワードについて触れてまいります。
(文責)小杉 雅芳
第二百七回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説(2021年12月6日)
令和3年12月6日 第二百七回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)
デジタルインフラを巡る現状と課題(2021年4月)
2022.09.05
その2:データセンター(DC)とカーボンニュートラル
カーボンニュートラルへ向けた再生可能エネルギー等の取組みの状況
現在、日本に限らず発電への依存が最も大きいのが化石燃料による発電です。石炭、石油、天然ガス等の化石燃料は、発電する代償として、大量のCO2を大気中に放出することが問題となり、地球温暖化を食い止める観点から世界中でCO2削減が叫ばれています。自動車、航空、運輸産業等においても同様で、化石燃料に代わるエネルギー源を模索し、開発・研究に力を入れている状況です。
また、元々エネルギー資源の乏しい日本においては、1980年代から原子力発電への舵取りに踏み切ったものの、福島第一原発事故に伴い、今後、原子力発電へ依存するか否かは不透明な状況となっています。
このような状況下、今一番注目されているのが再生可能エネルギー(以下、再エネという)の活用です。再エネには太陽光、風力、バイオマス、地熱、潮力、水中、その他と多岐に渡りますが、最も一般的に活用されているのが、太陽光発電です。太陽光発電はDCと一緒になって活用されるケースが日本でも最近は多くみられるようになりました。ただ、再エネの発電効率を考えると、現時点ではカーボンニュートラルと言えるには程遠く、結局のところは化石燃料由来の電力会社の電力に依存せざるを得ないのが現状です。
ところで、メガクラウドベンダーと言われるGAFAMの動向について触れてみると、マイクロソフトは、2030年までに「カーボンネガティブ」にする計画を発表しています。アマゾンは2025年までに再エネを100%使用することをコミットしており、Googleは同社の全てのDCでPUE値が1.1を下回っており、他社DCより消費電力が少なく、業界平均をはるかに下回っていると発表しています。
では、何故メガクラウドベンダーはこのようなカーボンニュートラルの施策が可能となるのでしょうか。ひとつは、北欧エリアの豊富な再生可能エネルギーを活用(開発や再エネの購入)していると共に、同エリアにDCを誘致して、寒冷地DCを実現していることにあります。また、アメリカ大陸においては、広大な土地を活用して、太陽光の大量発電とセットでDCを誘致し、再エネで電力を賄う規模で開発されている状況です。残念ながら日本において同様のDC開発は地理的観点から難易度は高く、実現性が乏しい先例となります。日本には日本に合ったカーボンニュートラルを実現するほかありません。そのためには、再エネの技術開発により一層注力して、例えば、水素、メタン、アンモニア等を活用して、再エネ分野で発電効率を上げることが重要と考えています。そして最も重要なのが、日本におけるDCの寒冷地エリアへの地方分散の実現です。
日本において寒冷地DCとして、高スペックの機能を発揮しているのが、さくらインターネット株式会社の石狩DCと株式会社データドックの新潟・長岡DCに代表されるものがあります。これらのDCは寒冷地特有の外気冷房方式を採用して、PUE値が1.2を下回る数値となっています。また、京セラコミュニケーションシステム株式会社は、再生可能エネルギー100%で運営するDCを石狩市で開業します。
このように、DCのカーボンニュートラル実現への近道は、寒冷地を中心としたDCの地方分散化が近道であり、国もDCの最適配置に向けて舵を切っている真っ只中にあります。
(その3)では、DCの最適配置に向けての地方分散と現状の矛盾について触れてまいります。
(文責)小杉 雅芳
2022.09.05
その1:データセンター(DC)とカーボンニュートラル
今回はカーボンニュートラルなDCの実現の観点から考察してみたいと思います。
DCはサーバーやネットワーク機器類などを安全かつ安心して格納することを目的として作られる施設(不動産)です。サーバーは大量の電力消費が必要な機器です。よって、DCでは大量の電力が消費されます。加えて、サーバーは大量の熱を発生するため、サーバーを正常に稼働させるためにはDC内を一定温度に管理する必要があります。つまりDCはサーバーのみならず、空調機器も大量に電力を消費する、カーボンニュートラルの観点から、大変厄介な施設と言えます。
大雑把なデータですが、日本国内電力消費の約1.4%(2018年)をDCが消費していると言われており、2030年には2018年比6倍以上になるとの分析もあります。※
世界におけるデジタルインフラ分野の成長加速は不可欠で、その中でDCは重要な位置付けになる一方、CO2排出の観点で悪役にもなり兼ねません。
DCとカーボンニュートラルの両立は、はたして成しえることが可能でしょうか。
DCの電力消費をみる一つの指標としてPUE(Power Usage Effectiveness=DC全体の消費電力/IT機器の消費電力)があります。1.0に近ければ近いほど、IT機器以外の消費電力が少なく、効率的なDCということになります。
一昔前のDCのPUEは2.0前後であると言われていましたが、最近竣工しているDCのスペックを見ると、PUE=1.4程度のものが主流となっているようです。また、これから着手するDCにおいては、PUEが1.2を下回る設計値を謳っているものも目立ち始めました。
このようにPUE値が下がり、1.0に近づいている要因は、①空調機器等の性能の向上、②サーバールームの効率的冷却を実現するための設計レベルの向上です。ただ、PUE値を押し下げるにはもっと重要な点があります。それはDCが立地する自然的条件です。
サーバールームは一般的に室温を20℃〜27℃に保っておく必要があるため、空調機器類が最も電力を消費するのは真夏で、且つ昼間の外気温が高温になる時間帯です。DCの立地が寒冷地であれば、大都市と比べ空調効率も良く、更に日中夜の寒暖差が大きいところでは、夜は外気を活用した冷却も可能となります。つまり寒冷地等の地方の立地では、空調機器を極力利用せずにサーバールームの室温を管理することが可能となり、空調機器を使用しない分、PUE値改善に大きく貢献することとなります。
このように、DCを開発する事業者等はCO2削減、カーボンニュートラル社会に向けて鋭意努力していますが、DCは大量の電力消費が不可欠であることは変わりません。
次回のブログ(その2)では、カーボンニュートラルを目指したDCの再生可能エネルギー活用の取組みにつきご紹介したいと思います。
(文責)小杉 雅芳
- 総合資源エネルギー調査会(経済産業省:令和4年3月)
2026.01.26
KDDI、大阪堺データセンターが稼働開始 〜AI需要をにらむ内資系データセンター事業の本格始動〜
通信大手のKDDIは2026年1月22日、大阪府堺市に新設した「大阪堺データセンター」の稼働を開始しました。これにより、AI処理需要の増大を背景に国内のデータセンター(DC)事業が再び動きを見せています。ここ数年目立った新設がなかったKDDIのDC事業ですが、昨今のAIインフラ需要を踏まえた戦略的な一歩と捉えられています。

大阪堺データセンター外観
シャープ堺工場跡地の再活用と短期間構築
大阪堺データセンターは、2025年4月にKDDIが取得した旧シャープ堺工場の跡地に構築されました。広大な敷地に元々備わっていた大規模な電力・冷却インフラを再利用することで、約半年という短期間での稼働開始を実現しています。従来のDC構築で必要となる長期の設備整備を大幅に圧縮できた点は、他社事業者との差別化要素として注目されます。
この施設は地上4階建て、延床面積約57,000平方メートルと大規模で、使用電力は100%再生可能エネルギー由来とする環境配慮型の設計も特徴です。電力供給と冷却は直接液体冷却(DLC)方式を取り入れ、高性能計算処理と低消費電力の両立を図っています。
AI処理インフラとしての機能強化
新データセンターには、NVIDIA製のAIサーバー「GB200 NVL72」など最新世代GPUサーバーが導入されており、AI学習や推論処理に最適化されたインフラとして位置づけられています。さらに、Googleの生成AIモデル「Gemini」のオンプレミス提供など、パートナー企業との協業を通じたサービス開発基盤としても活用される計画です。
法人企業向けにはGPUリソースの提供も行われ、多様な業界でのAI社会実装を支える役割が期待されています。特に製薬や製造などデータ量が巨大になりやすい分野では、高度な計算基盤のニーズが強まっており、KDDIはこの流れを捉えた形です。
30年以上の知見の集積と国内DC事業の潮流
KDDIはTelehouse渋谷データセンターで培った水冷技術やDC構築のノウハウを活用し、大阪堺データセンターの設計・運用に生かしています。これにより、高い稼働率や安定性を保ちながらも、新技術対応への柔軟性を確保しています。
国内ではソフトバンクも旧工場跡地を活用した大型DCプロジェクトを進めており、内資系事業者による大型インフラ投資の動きが活発化していることが読み取れます。AI処理需要の高まりを背景に、データセンター事業は従来の通信インフラの枠を超え、産業全般のデジタル基盤としての重要性を増しているといえるでしょう。
2026.01.19
グッドマンが日本で加速するデータセンター展開
物流ファンドのグッドマンは、これまで物流施設を中心に日本各地で事業展開を進めてきましたが、近年はデータセンター(DC)事業への進出を着実に進めています。特に千葉・茨城・神奈川圏を中心に、先進的なデジタルインフラの整備が進展しており、日本国内のデータセンター事業に新たな潮流を生み出しています。
印西におけるSTT GDCとの協業
千葉県印西市は、東京都心からのアクセスが良い立地と安定した電力供給などを背景に、データセンター集積地として知られています。こうした環境を活かし、シンガポール発のデータセンター事業者であるSTテレメディア・グローバル・データセンターズ(STT GDC)が、グッドマンの開発する施設内でデータセンターを展開しています。
2025年には日本国内初となる「STT Tokyo 1」が稼働し、約32MWのIT電力を提供可能な大規模DCとして運用が始まりました。将来的には同キャンパス内で2棟目となる「STT Tokyo 2」も建設され、さらなる処理能力の拡充が見込まれています。
このように、グッドマンが開発する施設をSTT GDCが活用する形で、先進的なデータセンターインフラの早期整備が進んでいます。
つくばにおける大型キャンパスの計画
一方、グッドマンは茨城県つくば市でも大規模なデータセンターキャンパスの計画を進めています。つくば市では広大な敷地を活用し、1棟目のデータセンターが2026年に完成予定です。このキャンパスでは最大1000MW級の電力供給体制を視野に入れ、段階的に複数棟のDC建設が進められる構想とされています。
つくばは先端研究機関が集積する科学都市としての特性を持ち、AIやクラウド関連の需要増加とも相まって、データセンター立地としての優位性が高まっています。
相模原での展望と地域期待
神奈川県相模原市に関しては、現時点で公式な建設計画の発表はありませんが、地元ではグッドマンによるデータセンター進出の可能性が取り沙汰されています。相模原は東京圏へのアクセスが良好で、道路・電力インフラの整備状況からもDC立地に適した条件を備えており、今後の動向に注目が集まっています。
デジタル基盤を支える拠点戦略
グッドマンのデータセンター展開は、物流施設を中心とした従来の事業領域から、デジタルインフラの整備へと領域を広げている点が特徴です。印西でのSTT GDCとの協業、つくばでの大規模キャンパス整備、そして相模原での期待感と、複数地域での動きが連動しながら、日本のデータセンター基盤の充実に寄与しています。今後も各地域での展開が進むことで、国内のデジタル基盤はさらに強化されていくと見込まれます。
海外プレイヤー参入の可能性と市場環境の変化
今後の日本市場では、国内デベロッパー主導の開発に加えて、海外の通信・データセンター系プレイヤーとファンドが連携して参入してくる動きが更に活発化してくると考えられます。たとえば、不動産ファンドのSC Capital Partners と海外でデータセンター開発・運用を手がけるSC Zeus Data Centersが、首都圏近郊の電力・用地条件に着目し、日本での拠点構築を積極的に展開しつつあります。AI・クラウド需要の拡大を背景に、日本のデータセンター適地は国際的にも魅力を高めています。
また、アジア太平洋地域で強いプレゼンスを持つ通信事業者である シンガポールテレコム(Singtel)についても、グローバルネットワークとデジタルインフラ投資の延長線上で、日本市場との関わりを今後深めていく可能性があると見られます。こうした海外勢の動きは、国内データセンター市場の競争環境や開発スピードに影響を与える要因のひとつになっていくでしょう。
こうした中で、日本でのデータセンター開発を検討する事業者にとっては、用地条件や電力インフラ、行政対応など、日本特有の環境を踏まえた検討がより重要になります。
2025.12.23
2025年のデータセンター市場を振り返る―多様なプレイヤーが動いた一年
2025年のデータセンター市場は、結果としてこれまで以上に多様なプレイヤーが参入し、プロジェクトの大規模化が一段と進んだ一年となりました。生成AIの急速な普及やクラウド利用の拡大を背景に、日本市場は国内外の事業者から中長期的な成長が見込まれる市場として改めて注目を集めました。
この年を通じて特徴的だったのは、参入主体の広がりです。従来は国内大手事業者や一部の外資系企業が中心でしたが、2025年は不動産デベロッパー、インフラ投資ファンド、通信関連企業、さらには海外で豊富な運営実績を持つデータセンター専業事業者など、背景の異なるプレイヤーが同時に存在感を高めました。
また、施設の在り方も変化しました。単なるコロケーション提供にとどまらず、AIワークロードを前提とした高電力・高密度設計や、ハイパースケーラー対応を見据えた大規模キャンパス型開発が進み、市場全体として「多様化」と「大規模化」が並行して進んだ一年だったと言えるでしょう。
立地面でも動きがありました。首都圏や関西圏の既存エリアに加え、新たな地域や準主要都市への進出が相次ぎ、日本国内のデータセンター立地はより広域的な広がりを見せました。
2025年を象徴するデータセンター各社の動き
2025年の市場動向を象徴する事例として、ESRの動きが挙げられます。ESRはStack InfrastructureやColt DCSとの連携を通じて、大阪・南港という新たなエリアへ進出しました。これは、関西圏におけるデータセンター立地の選択肢が広がったことを示す象徴的な動きでした。
Gaw CapitalとDayOneの連携も、2025年を特徴付ける動きの一つです。シンガポール系資本を背景に持ちながら、本社は中国に置くデータセンター事業者であり、日本市場にはこの年が実質的な初進出となりました。GDSを含め、中華系データセンター事業者の存在感が日本でも可視化された一年だったと言えます。
さらに、FLOW Digital InfrastructureやEdgeConneXといったグローバルなデータセンター専業事業者も、2025年に日本市場へ初めて参入しました。海外市場での運営ノウハウを持つ事業者が相次いで日本に拠点を構えた点は、市場の成熟度が一段階進んだことを示しています。
Global Compute Infrastructure(GCI)は北九州への進出を通じて日本市場に参入し、地方都市におけるデータセンター開発の可能性を具体的に示しました。また、Princeton Digital Group(PDG)は、さいたま市において初の大型データセンター開発を進め、首都圏近郊における大規模案件として存在感を高めました。
2025年は、多様なプレイヤーがそれぞれの強みを持ち込み、日本のデータセンター市場に新たな選択肢と広がりをもたらした一年でした。こうした動きは、今後のデータセンターの在り方や立地戦略、事業モデルを考える上で、重要な示唆を与えるものとなっています。
2025.12.21
生成AI時代、データセンター建設費という新たな注目ポイント
生成AIの普及を背景に、データセンターを取り巻く環境は大きく変化しています。これまでデータセンターの課題としては、電力需要の増大や電力インフラの確保が注目されることが多くありましたが、近年ではそれに加えて「建設費」の動向にも関心が集まりつつあります。
こうした中、ターナー&タウンゼントが発表した最新の調査では、世界各都市におけるデータセンター建設コストが比較され、日本の都市が非常に高い水準にあることが示されました。特に東京は、1ワットあたりの建設費が世界でもトップクラスとされており、日本市場の特徴を改めて浮き彫りにする結果となっています。
生成AI向けのインフラ需要が拡大する中で、データセンターの建設費は、今後の投資判断を考える上で無視できない要素となりつつあるようです。
建設費が高水準となる背景
今回の調査では、日本のデータセンター建設費が高水準となっている背景として、いくつかの要因が挙げられています。その一つが、生成AI対応に伴う設備要件の高度化です。高密度なサーバー配置に対応するため、電力供給設備や冷却設備の仕様が引き上げられ、結果として建設費全体が押し上げられています。
また、電力・空調・IT設備といった専門分野に対応できる人材の確保が難しくなっている点も、コスト上昇の一因とされています。加えて、海外からの資材調達や為替の影響を受けやすい構造もあり、こうした複合的な要素が日本の建設費水準に反映されていると考えられます。
今後の動向として注目されるポイント
生成AI市場の成長が続く中で、データセンター需要は今後も堅調に推移すると見込まれています。それに伴い、建設費についても短期的に大きく下がるというよりは、高水準で推移する可能性があるとみられています。
一方で、こうした状況を受けて、建設手法やプロジェクト管理の工夫によってコストの最適化を図ろうとする動きも出てきています。建設費の動向は、電力や立地と並ぶ重要な検討項目として、今後さらに注目されていくことになりそうです。
生成AIの時代において、データセンターを支えるインフラの在り方は引き続き変化していきます。その中で、建設費という視点から市場動向を捉えることは、今後のデータセンターを取り巻く動きを理解する上での一つの参考材料になるといえるでしょう。



 EN
EN