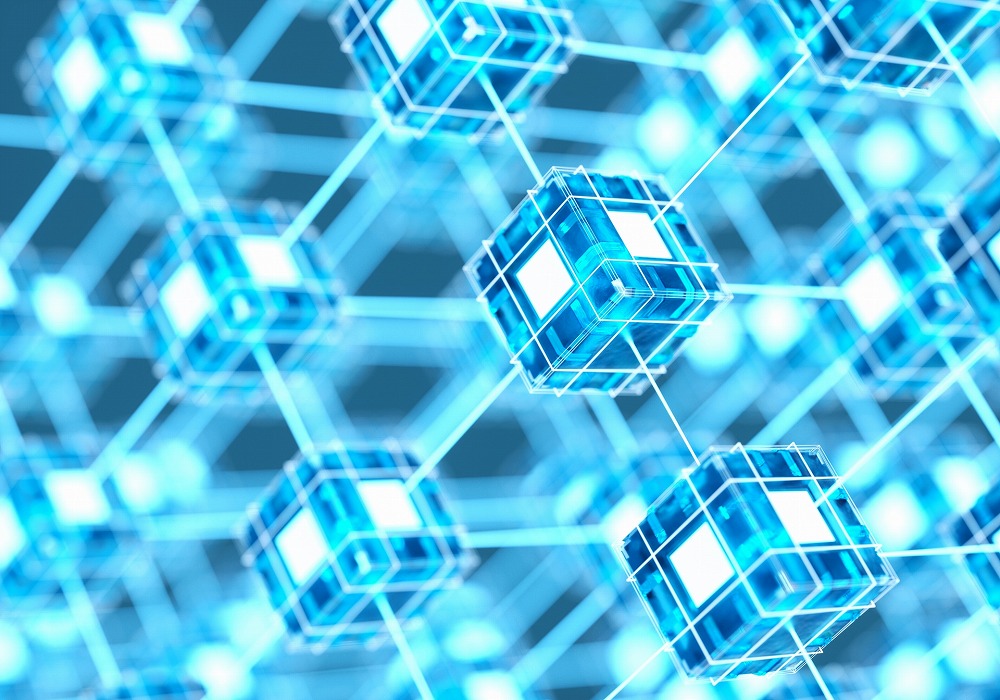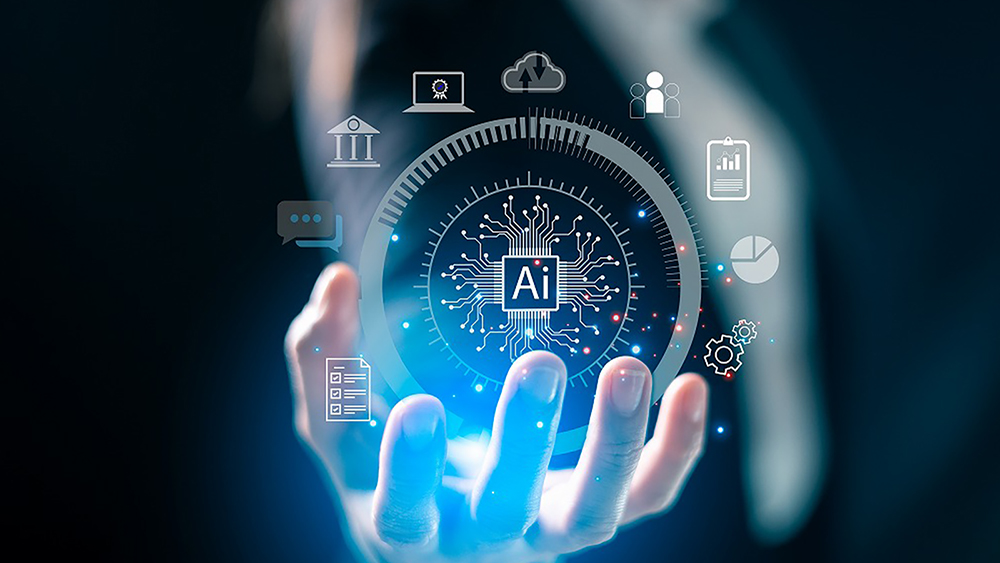News & Topics

電力インフラとデジタル基盤が交差する時代
近年、生成AIやクラウドサービスの急速な普及を背景に、国内データセンター需要は拡大基調にあります。国内のデータセンターが必要とするIT機器向けの電力容量は、2024年末の約2,365MVAから2029年末には約4,499 […]
TOPICS & NEWS
2026.02.26
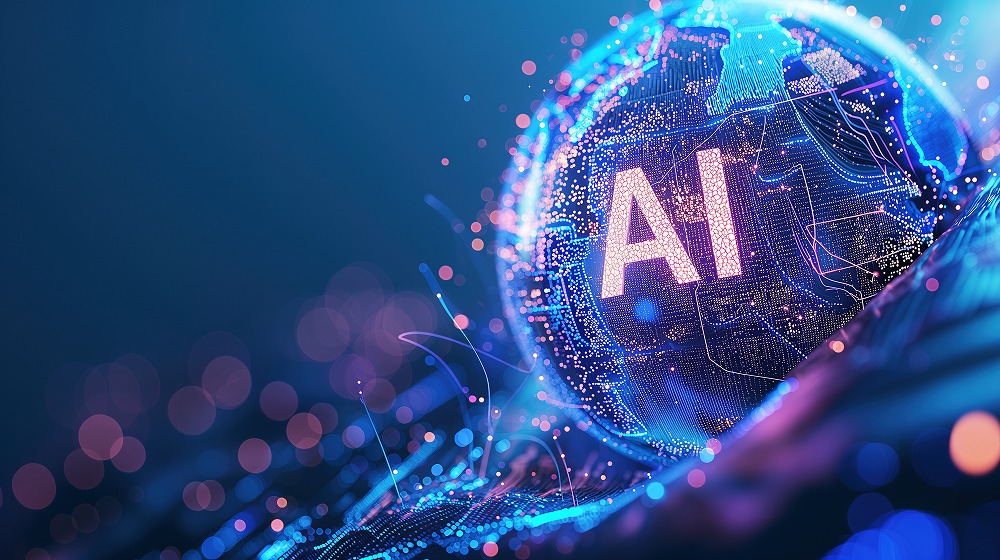
ソフトバンク、AI時代のデータセンター戦略を加速 ~インフラ革新でデジタル社会の未来を切り拓く~
近年、生成AIや機械学習の普及に伴い、大規模なデータ処理基盤としての AI対応データセンター(AI用DC) の重要性が著しく高まっています。こうした変革を見据え、ソフトバンク株式会社は次世代インフラの中核となるデータセン […]
TOPICS & NEWS
2026.02.24

KDDI、大阪堺データセンターが稼働開始 〜AI需要をにらむ内資系データセンター事業の本格始動〜
通信大手のKDDIは2026年1月22日、大阪府堺市に新設した「大阪堺データセンター」の稼働を開始しました。これにより、AI処理需要の増大を背景に国内のデータセンター(DC)事業が再び動きを見せています。ここ数年目立った […]
TOPICS & NEWS
2026.01.26

グッドマンが日本で加速するデータセンター展開
物流ファンドのグッドマンは、これまで物流施設を中心に日本各地で事業展開を進めてきましたが、近年はデータセンター(DC)事業への進出を着実に進めています。特に千葉・茨城・神奈川圏を中心に、先進的なデジタルインフラの整備が進 […]
TOPICS & NEWS
2026.01.19

2025年のデータセンター市場を振り返る―多様なプレイヤーが動いた一年
2025年のデータセンター市場は、結果としてこれまで以上に多様なプレイヤーが参入し、プロジェクトの大規模化が一段と進んだ一年となりました。生成AIの急速な普及やクラウド利用の拡大を背景に、日本市場は国内外の事業者から中長 […]
TOPICS & NEWS
2025.12.23

生成AI時代、データセンター建設費という新たな注目ポイント
生成AIの普及を背景に、データセンターを取り巻く環境は大きく変化しています。これまでデータセンターの課題としては、電力需要の増大や電力インフラの確保が注目されることが多くありましたが、近年ではそれに加えて「建設費」の動向 […]
TOPICS & NEWS
2025.12.21

ソフトバンクが描く次世代社会インフラ-AIデータセンターが切り開く新たな基盤づくり
ソフトバンクは近年、通信事業者という枠を超え、AI時代の社会基盤を担う企業へと進化しようとしています。その中心となっているのが、全国に分散配置されるAIデータセンターと、通信・計算処理を統合した次世代インフラ構想です。同 […]
TOPICS & NEWS
2025.12.20

鹿児島で進む大規模データセンター計画 ─ 原発立地の特性とワットビット連携に見る先行性
鹿児島県で進められている大規模データセンター計画が、業界内で大きな注目を集めています。計画地は九州電力川内原子力発電所に近く、電力供給面で高い安定性が見込まれるのが特徴です。AI開発や半導体製造の高度化が進む中で、データ […]
TOPICS & NEWS
2025.11.20



 EN
EN